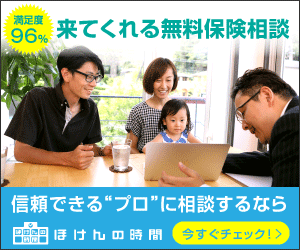・年金制度のしくみは?
・日本の年金制度の未来についてわかりやすく知りたいです!
本記事の結論
- 日本の年金制度は崩壊しない
- 日本の年金は賦課方式
- もらえる額が減る可能性はある

そもそも年金制度とは?
年金制度とは
現代日本では公的年金に対して、ネガティブな論調が優勢ですが、当記事では、そんな日本の年金制度の未来について検証します。
賦課方式と積立方式
公的年金には、賦課方式と積立方式の2種類があります。
日本の年金制度は賦課(ふか)方式を採用しています。
賦課方式とは、働く現在現役の人が払い込んだ金を現在の高齢者に支給する仕組みであり、この賦課方式によって「世代間扶養」が実現できる。
Wikipediaより引用
現役世代が納めたお金は国に積み立てたものを老後に年金として受け取る訳ではありません。
これは積立方式と呼ばれる仕組みです。
日本の公的年金が採用している賦課方式とは、
現役世代が高齢世代の年金を負担する
という仕組みです。
したがって日本の公的年金は、基本的に賦課方式を採用(一部積立金を運用)している為、現役世代が高齢世代の年金給付金を納めている事になります。
それでは、賦課方式と積立方式それぞれのメリットとデメリットを確認します。
賦課方式
●メリット
インフレによる貨幣価値の変動に強い
●デメリット
人口構造の変化に弱い
世代間の公平分配に弱い
賦課方式は、現在の現役世代が現在の高齢世代の年金受給額を負担しますから、インフレに強い仕組みと言えます。
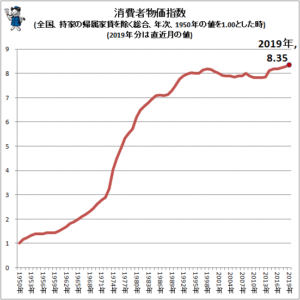
画像:ガベージニュース
これは、1950年を1とした消費者物価指数の推移です。
参考記事:消費者物価指数とは?
正式に公的年金が開始された1961年から、日本の物価は約8倍に上がっています。
つまり
お金の価値は約8分の1
になっているのです。
これは、1960年に100円で買えた物が、現在は800円まで物価が上がっているという事です。
このようにもし、日本の公的年金が積立方式であれば、長年にわかって積み立てた保険料の価値が大きく損なわれる可能性があります。
賦課方式は、保険料の納付と給付が同時期である為に、その時点での貨幣価値でやりとりされますので、インフレに強いと言われるのです。
一方で、賦課方式は人口減少には弱いという特徴があります。
少子高齢化によって現役世代が減少し、高齢受給者が増加する事によって、現役世代への納付負担が大きくなる為です。
次に積立方式を解説します。
積立方式
●メリット
人口構造の変化に強い
●デメリット
インフレに弱い
前述した通り積立方式は、インフレに弱いです。
積立てたお金の貨幣価値がインフレによって下落してしまえば、将来受け取れる年金の受給金額の価値も下落してしまいます。
参考記事:インフレーションを詳しくはこちら
ただ積立方式は、現役時に積立てた金額が高齢者になった時に受給されるため、少子高齢化による世代間の受給における公平性は担保されます。
参考記事:少子高齢化の原因は?
ということは、公的年金が採用する賦課方式は日本が抱える様々な問題を被ってしまうのでしょうか?
日本の公的年金が不安視される本当の理由
それでは、なぜ現代日本では年金制度が不安視されているのかを、2つの理由に分けて解説します。
① 国家財政への不安
まず、公的年金への不安の根底には
そもそも日本の国家財政が大丈夫なのか?
という漠然とした不安が日本国民の世論に存在しています。
国の借金が1000兆円を超え、国民一人当たりに1000万円近くの借金が存在すると喧伝されていますので、無理もありません。
年金制度が積立方式と誤解しているならば、財政破綻した瞬間に積立金もすべてぶっ飛んでしまうと思う事でしょう。
ただ、日本は現在、財政破綻とは程遠い状態にあります。
国の借金や財政破綻の問題は、当ブログでは様々な所で記事にして来ました。
下記の参考記事2つをお読み頂ければ、日本は財政破綻には程遠いと言える理由がお分かり頂けるでしょう。
参考記事:国の借金とは?わかりやすく解説
参考記事:なぜ財務省は緊縮財政をやめないのか?
むしろ、国家財政や将来を過度に不安視する事は、国内の消費と投資を抑制してしますので、国内経済には悪影響と言えます。
② 人口減少への不安
次に、日本の公的年金が賦課方式を採用している事から、人口減少、国内景気が年金制度に及ぼす悪影響に対して、漠然とした不安が存在していると言えます。
人口が減少して少子高齢化が進めば、当然若者一人当たりの保険料負担は増えてしまいます。
そうなれば、手取り所得の減少から消費が減退したり、保険料の未納が増えるかもしれません。
このような漠然とした不安が、将来不安を生み、公的年金にも懐疑的になってしまっているのです。
しかし、本当にそうでしょうか?
ここからは、年金の性質を極力シンプルに、説明します。
年金数理
年金とは一つの保険です。
単純化すれば、
20歳から60歳まで保険料を納付し
60歳から80歳まで年金を受け取る仕組
です。
あくまで年金は保険ですから、納付した金額と受け取る金額が長期的に均衡するように計算されています。
(20歳〜60歳) 納付額
=
(60歳〜80歳) 受給額
このような計算、理論は年金数理と呼ばれます。
年金数理
年金制度において長期的な財政計画を立てる際の数学的理論や計算方法を総称して年金数理といいます。
その大前提は、保険料、積立金の運用収入、国庫負担の収入総額と年金給付の支出総額が長期的に均衡する「収支相等の原則」です。
出典:weblio
実は日本の年金制度はこの年金数理を元に、毎年調整しながら運用されているのです。
もちろん、これは単純化した説明なので、実際に80歳よりも長く生きる人もいれば、不幸にも受給せずに亡くなってしまう人もいます。
不幸にも60歳で亡くなってしまえば今までの納めた保険料はすべて消失し、100歳まで長生き出来れば得をするのです。
つまり、
公的年金とは早く亡くなる人から
長生きの人への資金移転
と表現できます。
このように年金制度は数学的な問題で
人口予測さえ間違わなければ破綻する事はありません。
とは言え、人口減少に歯止めがかからなければ、様々な調整の結果の受給額が少なくなる事も考えられます。
最後に、年金制度をより安定的に運用する方法を明らかにします。
日本の年金制度への処方箋
今の若者世代もしっかりと老後を安心して暮らせる受給額を貰えるようにするポイントが一つだけあります。
それは
正しい経済政策による経済成長
これだけです。
年金制度の未来を語るときに
『将来は若者2人で高齢者1人を支える事になる』
と言った表現があります。
これは、人口予測で考えるとそうなりますが、誤解を生む表現といえます。
なぜなら、年金はお金の問題なので人数ではなく、金額で考えるべきだからです。
例えば、将来こ若者が2人で1人の高齢者を支えるとしても、その若者の収入が今の若者の収入の2倍あるとすればどうでしょう?
高齢者はしっかりと年金を受給されますし、若者も年金を納付しながら豊かな生活が出来る事でしょう。
未来の若者の収入が上がる方法は、ただ一つです。
GDPを拡大し、経済成長させる
これが、年金制度を安定して維持させる『解』です。
日本が普通の先進国並み(2%〜3%)の経済成長を遂げられれば、現在の少子高齢化を織り込んだとしても、何の問題もなく年金制度は続けられる試算が出ています。
それでは、どのような経済政策によって日本を経済成長させれば良いのでしょうか?
当サイトにて紹介していますので参照頂ければと思います。
参考記事:大胆な金融政策とは?
正しい経済政策がしっかり行われて、日本が『普通の先進国並み』の経済成長ができれば、日本の公的年金は何の問題もありません。
むしろ、年金制度への悲観的な未来が蔓延して、消費や投資、人口減少が悪化してしまえば、これは日本経済に悪影響となってしまいます。
正しい知識を持ち、過度に悲観的な情報に流されず、楽観を捨てずに未来に臨む姿勢が大切だと、私は考えています。